診療技術部の紹介
当院の診療技術部は5つの部署(薬剤科・放射線科・臨床検査科・栄養科・リハビリテーション室)から構成されています。
各職種が高度な専門知識・技術・能力の向上に努め、チーム医療の一員をして一丸となり、患者ファーストの医療を心がけています。
お知らせ
-
2025.12.26 おしらせ
-
2025.12.26 おしらせ
-
2025.07.11 おしらせ
-
2024.12.20 おしらせ
関連記事
現在、記事はございません。
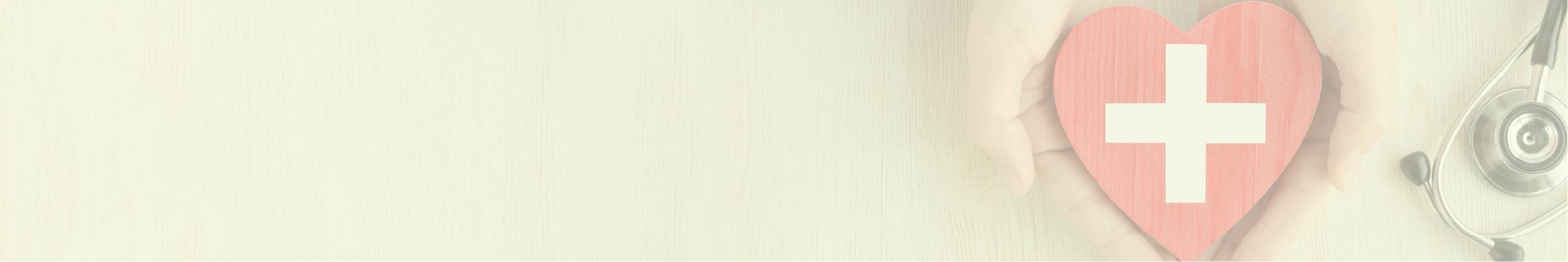
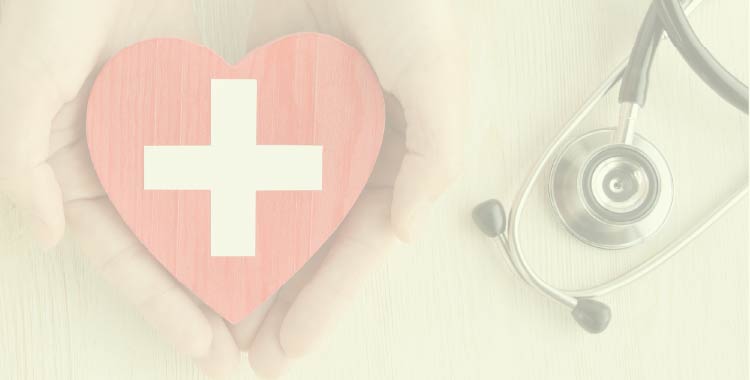
当院の診療技術部は5つの部署(薬剤科・放射線科・臨床検査科・栄養科・リハビリテーション室)から構成されています。
各職種が高度な専門知識・技術・能力の向上に努め、チーム医療の一員をして一丸となり、患者ファーストの医療を心がけています。
現在、記事はございません。